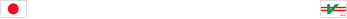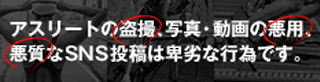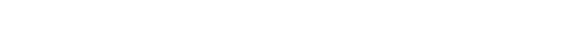【担当記者が見たレスリング(4)】男子復活に必要なものは、1988年ソウル大会の“あの熱さ”…久浦真一(スポーツ報知)
(文=スポーツ報知記者・久浦真一)
レスリングで最も印象に残っているのが、1988年のソウル・オリンピックだ。この大会、全競技を通じた日本選手の成績は振るわず、金メダルは4個に終わった。その中で存在感を示したのがレスリングだった。フリースタイル48kg級の小林孝至と同52kg級の佐藤満がともに金メダル、フリースタイル90kg級の太田章とグレコローマン52kg級の宮原厚次がともに銀メダルの好成績を収めた。
大会前、日本レスリング協会は異例とも言える500日の長期合宿を敢行した。1987年4月27日、東京・渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターに代表候補16人らが集まり、スタートさせた。協会は「いつでも取材に来て下さい。真夜中でも大丈夫です。選手をたたき起こしても結構です」と、脈々と続く“マスコミを大事にする八田イズム”を報道陣にアピールした。
2人が金メダルを獲得できた要因のひとつに、強烈なライバル意識があったと思う。小林の日大に対して、佐藤の日体大。大学2強のエネルギーが良い形で実を結んだ。小林のスパーリングパートナーが富山英明コーチ(現日本協会副会長)、佐藤に高田裕司コーチ(現日本協会専務理事)がついていた。
ともに、オリンピック金メダリスト。これほど贅沢な練習相手はいなかっただろう。そのぶつかり合いは、火の出るようなスパーリングだった。それは、ともに「負けてたまるか」「必ず金メダルを取る」という気持ちが、見ていても分かるような激しさだった。
理事会と真っ向から闘った花原勉強化委員長
花原勉強化委員長(1964年東京オリンピック金メダリスト)も体を張っていた。オリンピック代表の選考課程で理事会と現場が食い違いを見せる時があった。私はそのことを原稿にし、批判した。理事会が押し切りそうな勢いだったが、花原強化委員長はそれを押し返し、当初の選考方法に落ち着いた。
後日、現場で私に「ちゃんとやったでしょう。私は決まったことは守るんですよ」と言って、ニヤリと笑った。
迎えたソウル・オリンピック決勝。小林は一瞬ヒヤリとする場面はあったものの、イワン・ツォノフ(ブルガリア)を破り、佐藤は、1984年ロサンゼルス大会で高田コーチが敗れたサバン・トルステナ(ユーゴ)に完勝し、ともに金メダルを獲得した。
富山コーチに肩車された小林、高田コーチにかつがれた佐藤。記者席から見たその姿は忘れられない。レスリング最終日には、打ち上げにも同席させてもらった。「一緒に頑張ったんだから、一緒に祝杯をあげましょう」と、声をかけられた。
協会とマスコミが一体となり、絶妙なバランスだった
当時は、協会とマスコミが一体となっていたと思う。先に挙げた花原強化委員長との件でもそうだが、緊張関係を保ちつつ、言いたいことは言い合う関係だった。余談だが、私が練習の取材に行くと、なぜか、必ず富山さんにつかまり、マットに転がされるのがお約束だった。
「僕のこと書いて下さいよ」とアピールしてくる選手も珍しくなかった。取材における距離感が近かったし、熱かった。その結果が、金メダル2個につながったと今でも思っている。
選手と所属のライバル関係。それをきちんと統括した強化委員長。それを見守るマスコミ。そのバランスが絶妙だったのではないか。その後、長期低迷し、2012年ロンドン大会の米満達弘までオリンピックの金メダルは途絶え、女子に主役の座を奪われた。
しかし、私は今も信じている。あの時の熱さがあれば、「やっぱり男子レスリングはすごいね」と言われることを。
| 久浦真一(ひさうら・しんいち) 1960年、佐賀県唐津市出身。中大卒。1984年、報知新聞社入社。レスリング、バレーボールなどのオリンピック競技やラグビーなどを担当。オリンピックは、1988年ソウル、1998年長野(冬季)、2000年シドニーの各大会を取材。運動第二部部長、編集局次長、編集委員等を歴任。 |
担当記者が見たレスリング
■2020年5月16日: 語学を勉強し、人脈をつくり、国際感覚のある人材の育成を期待…柴田真宏(元朝日新聞記者)
■2020年5月9日: もっと増やせないか、「フォール勝ち」…粟野仁雄(ジャーナリスト)
■2020年5月2日: 閉会式で見たい、困難を乗り越えた選手の満面の笑みを!…矢内由美子(フリーライター)