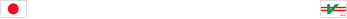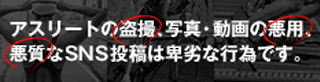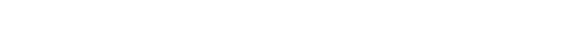【新春特集】永田克彦さん&浜口京子さんが熱きメッセージ(3)
(司会=布施鋼治/対談撮影=保高幸子)
学生王者~全日本王者の兄の背中を追った(永田さん)
――永田さんも悔し涙は何度も流しましたか?
永田 男は人前で涙を見せるな、と言われて育った世代ですので、大泣きすることはなかったですが、悔しいという気持ちは何度も経験しました。早く勝つ喜びを味わいたい、表彰台の一番高いところに上がりたい、という気落ちは強かったです。
――兄(現プロレスラーの永田裕志さん)からの励ましは?
永田 無骨に「頑張れよ!」と言うだけでした(笑)。大学はすれ違いですから、直接の技術指導を受けたことはないです。ただ、兄は大学2年生で学生王者になっていて、その後全日本チャンピオンにも輝いていますので、その背中を追ったという面はあります。身近にそういう人間がいたとこでエネルギーにはなりましたね。
浜口 その面で、兄弟や姉妹で同じスポーツをやるのはいいですね。私の弟は、最初は別のスポーツをやっていましたが、途中からレスリングを始め、練習相手にもなってくれました。弟がそばにいて練習できるというのはプラスになりました。技術面とかを含めて多くのことを話せました。ギリシャのハルキダで行われた世界選手権(2002年)あたりから練習パートナーになってくれて、復活優勝もできました。(私が)最重量級でしたので、体重80kg前後の弟との練習はパワーもつきました。北京オリンピックの選考会を兼ねた2007年の世界選手権では結果を出せなかった私に、試合会場で「レスリングをやりたいと思う時まで休んでみたらいいよ」と言葉をかけてくれたんです。プレッシャーが肩の上から落ちたようでした。2ヶ月後くらいに全日本選手権があったので実際には休めませんでしたが、弟の言葉はその後調子が上向きになるきっかけになりました。永田さんは男の兄弟なので、よかった面はなかったですか?
永田 ボクの場合は、兄とはレスリングをやっていた時期が違っていましたので、本格的に一緒に練習したことはないんです。ただ、自分がシドニー・オリンピックを目指していた時は、厳しめの激励をしてくれました。
――新日本プロレスで、海外修行から帰ってきてメーンイベンターを目指して上がっていく時ですね。
永田 上を目指す、という意味で同じ方向を向いていました。ちょっとした言葉でも刺激になりました。シドニー・オリンピックが終わって新日本プロレスの職員に転職し、アテネ・オリンピックを目指す時、兄との距離が縮まりました。セコンドにもついてくれるようになりましたし、大きな支えになりました。
――セコンドと言えば、アニマル浜口さんも熱く燃えましたね。
浜口 福田会長をはじめ、多くの方に門を開けて迎えていただきました。試合会場で大声を出すことは、それまでにはあまりなかったと思います。でも、父はウォーミングアップの時から大声を出していた。プロレスの経験からして、緊張をほぐす方法とかを父なりに考えての行動だったと思います。
人がやっていない練習だからこそ、自信になる(浜口さん)
――周囲に気を遣い、同じことをやる必要はないわけですね。
浜口 いろんなトレーニングも考えてくれました。原始的ではあっても、人がやっていないトレーニングだから、それがかえって自信になったりもするんです。キッズ時代からレスリングをやっているのが普通になった時代、勝つためにはそれしかなかったんだと思います。
永田 ボクの場合、最初に気がついた弱点と課題がフィジカル面でした。それを克服するために徹底したパワートレーニングに取り組みました。「一人でもやっていかなければ周囲に追いつけない」と思い、全体練習のあと大学のトレーニング場に毎日、一人で向かいました。周囲と同じことをやっていては、進歩はないと思います。
浜口 階級区分が変わったとき(1997年)、最重量級にすることを勧めたのが父です。その時はまだプロレスへ行くことも考えていましたが、体重を増やすためにパワートレーニングをしっかりやり、パワーをつけたのが、その後に役に立ちました。自分の持ち味を生かすことが一番必要なことだと思います。
――ともに、そうした努力を積み重ねて全日本チャンピオンになられたわけですが、そのときの気持ちはいかがでしたか?
浜口 明治記念館の宴会場での試合だったんです(1996年)。明治記念館ですよ。
永田 え~。レスリング協会の祝勝会とかをやる会場じゃないですか?
浜口 そうなんです。忘れもしません。決勝は斉藤紀江選手(茨城・土浦日大高柔道部)。前の年の全日本選手権で逆転フォール負けしていたので、リベンジ戦でもあったんです。ですから、すごく緊張していました。それを乗り越えて優勝できたことで、一皮むけましたね。
永田 明治記念館の宴会場での試合というのも、すごいですね。
浜口 決勝が始まると、会場の照明が落ちてマットだけ明るくなって、プロレスの会場みたいでした。(山本)美憂先輩も出ていたと思います(注=これは1998年の同所での大会)。ああいう場所だったので、みんな輝いていました。
永田 ボクの場合は、日本一になったことで、頑張ったことが結果につながったと思えて、うれしかったですね。表彰台の一番上から見た光景は何とも言えませんでした。目標を定め、揺るぎない気持ちでやっていけば結果は出る、と確信しました。男子は取材があまりなかった時代で、取材してもらった記者のことと、書かれた記事については、今でもしっかり覚えています。オリンピックは、日本一になっただけでは行けないわけで、予選を勝ち抜くためにさらに頑張ろうと思い、次の目標を定めました。
スポーツ新聞5紙が1面トップで扱った「浜口京子・世界一」
――当時、浜口さんは別格として、レスリングが一般メディアに扱われることは少なかった。マスコミに扱われることは、モチベーションの面でいかがでしょうか。
永田 それが目標ではないですけど、名前を残したい、知ってもらいたい、という野心はありましたよ。今より媒体は少ないですし、ネットもありませんでしたが、だからこそ活字になることはうれしかったですね。最初は、(一般メディアでなくとも)協会機関誌や専門誌でもいいから、取り上げてもらいたかった。
――そのあたりは、インスタグラムなどのSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)があって、自ら発信できる現在の選手は違う感覚かもしれませんね。
永田 ネットがなかったので、取材されてから記事ができるまで2週間、1ヶ月とあるわけです。どんな記事になるのかな、あるいはボツかな、とか思って、発売が楽しみでした。
――浜口さんは、世界選手権で初優勝したとき、スポーツ新聞5紙から1面トップ記事で扱われましたよね。
浜口 フランスから帰国して成田空港で新聞を見せてもらって、びっくりしました。「自分がこんなに扱われるなんて」と、うれしいというより、びっくりの気持ちの方が強かったです。「なんで自分が?」という信じられない気持ちでした。
――当時、スポーツ紙の一面はプロ野球の読売巨人軍が定番でした。巨人戦もちゃんとあった日なんですよ。一般新聞も一面の左上で掲載していましたし、NHKも扱ったそうです。
永田 すごいことですよね。スポーツ新聞5紙が一斉に一面トップ記事ですから。
浜口 それまでは、専門誌で扱われることはあっても、新聞に大きく扱われることはなかったです。世界一って違うんだな、と思いました。その3年前だったと思いますが、JOC杯で優勝した時、協会機関誌で「レスリング界のキョンキョン(当時人気絶頂だった歌手&女優、小泉今日子の愛称)」と書かれたことが印象に残っています。
永田 いいですね。
浜口 キョンキョンになれるのかな、と不安になりましたけど、記事にしていただいたことで、うれしく、頑張るエネルギーになりましたね。